【医師と技師が議論】STAT画像への対応と日頃からのコミュニケーション


記事の監修医師
【略歴】
熊本大学医学部卒業
【資格/役職】
放射線診断専門医 医学博士
株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO
医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長
熊本大学医学部 臨床教授
日々、多くの画像を目にする放射線技師。
その中で、命にかかわる、緊急性の高い所見を出さざるを得ない画像に遭遇することがあります。STAT画像と呼ばれるものです。
STAT画像に該当しそうな画像があった際、放射線技師はどう対応すればよいのでしょうか。また、放射線科医やその他の医師はSTAT画像を念頭に置いたとき、放射線技師と日ごろから何を想定しておけばよいのでしょうか。医師と技師が膝を突き合わせて議論しました。
STAT画像とは?
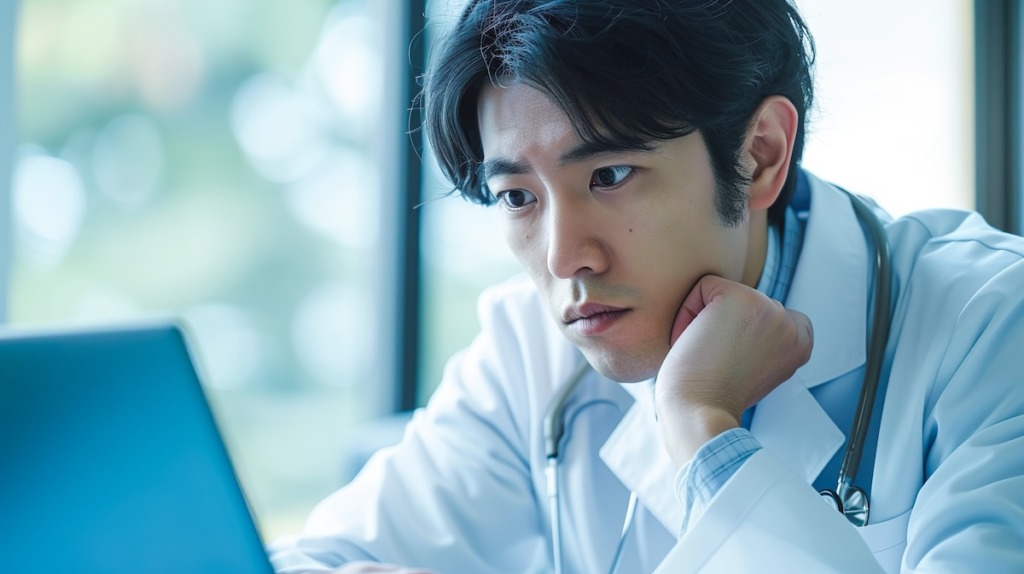
医師:STAT画像とは、MRIやCT検査などで撮影された画像の中に、脳出血や大動脈解離など、生命予後に直結する緊急性の高い疾患が疑われる所見が認められる場合、その画像を指します。
「STAT」という用語はラテン語の「statim」(直ちに)に由来し、医療現場では「直ちに医師の確認が必要な画像」として扱われます。
STAT画像は、患者の生命を脅かす異常所見を含み、迅速な治療介入を促すため、撮影直後に診療放射線技師が確認し、医師へ即座に報告する仕組みが採用されています。これにより、早期診断と治療開始が促進され、治療成績の向上や医療事故の防止、医療の質と効率の向上が期待されます。
また、STAT画像には放射線診断医が画像を正確かつ迅速に読影できるよう、診療放射線技師の専門知識を活かした読影支援の役割もあります。撮影後、まず画像に目を通す診療放射線技師が初見を判断し報告することで、緊急症例に対する対応が迅速化し、患者の生死に関わる場面での治療成果が向上します。
技師:確かに検査中、STAT画像に該当しそうな症例に遭遇すると、ひやっとする瞬間があります。そんなときでも焦らず冷静に対応し、速やかに医師や周囲スタッフに報告するなどの行動が重要だと感じています。
実際のSTAT画像とは?

技師:「放射線科医から診療放射線技師へのタスク・シフト/シェアのためのガイドライン集」には、STAT画像に該当する可能性のある具体的な疾患の一覧が掲載されています。例えば頭部MRI撮影時、拡散強調画像(DWI)で高信号/ADCmapで低信号を認めた際、脳梗塞疑いとして報告を行います。
医師:なるほど、ガイドライン集に掲載された具体例は非常に参考になりますね。例えば、頭部MRI撮影時にDWIで高信号、ADCmapで低信号が認められた場合に脳梗塞疑いとして報告するなどの基準は、診療放射線技師がSTAT画像の所見判断を迅速に行い、医師へ即報告するための明確な手順を示しています。
このガイドラインは、タスク・シフト/シェアの推進を目的として、報告プロセスや役割分担、必要な教育・訓練、チェック体制まで細かく定め、早期診断・治療開始による患者救命と医療現場の効率向上に寄与する一方、均質な教育プログラムの整備や法的リスク、施設間の運用差の解消といった課題も明示されていますね。
https://www.jart.jp/docs/ガイドライン_20240304_JARTJRSJCR.pdf
STAT画像に遭遇した際の対応

医師:放射線診断医がいない医療機関や、夜間・休日などで放射線診断医にすぐ連絡が取れないときに、緊急性の高いSTAT画像を見つけた場合、診療放射線技師はどのように対応しているのでしょうか?
技師:まずは撮影依頼をした担当医または看護師に連絡します。また放射線科情報システム(RIS)に撮影時、気づいたことの詳細をコメントとして記載し、後日放射線科医が出勤時に検査状況を確認できるよう対応しています。もし緊急度が高い場合などでは、我々技師や担当医が直接電話で放射線科医に相談するなど状況に応じた対応を心がけています。
STAT画像に関する放射線科内のコミュニケーション

技師:画像診断を行う現場と実際に治療を行う現場とで食い違いがあり、認識の違いがあるケースがあります。私は、臨床医が行うカンファレンスには積極的に参加するようにしています。日々のカンファレンスを通じて、臨床現場でどのような画像が求められているのか理解が深まります。
また技師同士、そして放射線科医と技師の連携や情報共有も非常に大切です。部内での定期的な勉強会やミーティングにて情報交換、意見交換を行っています。
医師:それはとても大切なことですね。カンファレンスや勉強会は、知識を深め、現場での対応力を高める貴重な機会です。臨床現場では、さまざまな状況下で撮影を行うことがあり、時には予想外のケースに直面し、どのような撮影方法が最適か、追加検査が必要かなど悩むこともあると思います。放射線診断医が近くにいれば相談できますが、不在時には診療放射線技師が自身で判断しなければなりません。そのため、日頃から放射線診断医がどのような視点で画像をみているのかを共有しておくことが大切です。
ワイズ・リーディングでも、定期的に症例検討会や勉強会を行い、放射線診断医とスタッフが意見交換できる場を設けています。
STAT画像を補完する遠隔画像診断の活用

医師:院内に放射線診断医が不在の場合、遠隔画像診断は大きな力を発揮します。ワイズ・リーディングの「Y’s Report」では、緊急依頼に対して3時間以内のレポート送付を徹底しており、さらにチャット機能を活用して臨床情報や追加情報のやり取りもリアルタイムで行える体制を整えています。これにより、現場の診療放射線技師や医師の負担を軽減しながら、より迅速で確実な診断支援を実現しています。
おわりに
診療放射線技師は、撮影した画像からSTAT画像の所見を見つけ出す重要な役割を担い、最終的な診断を行う放射線診断医や臨床医につなぎます。患者の状態が急変するタイミングは予測できず、診療放射線技師は日常の検査でも常にSTAT画像に備える必要があります。もし放射線診断医が不在の状況でSTAT画像を発見した場合は、落ち着いて対応し、速やかに臨床医へ報告することが大切です。また、所見の拾い上げに自信がない場合や放射線診断医の意見を聞きたい場合などには、遠隔画像診断の活用も有効です。
これにより、安心して迅速な対応ができる診療体制を整えることが可能になります。
放射線技師・医師向けのセミナーを不定期開催中!!
本メディアを運営するY’s READINGでは、放射線技師・医師向けのセミナーを不定期に開催しております。
症例画像を用いたディスカッション形式のワークショップ「ウェブラジエーション勉強会」や、次世代の人材育成をコンセプトにゲストを迎えて取り組む実践型セミナー「みらいクラブ」など、さまざまなテーマで実施しています。
医学部生や診療放射線技師はもちろん、その他の医療関係者など、興味のある方はどなたでもご参加いただけます。
一部のイベントを除き、Zoomよりオンラインでも参加可能なため、全国のみなさまのご参加をお待ちしております。
\ 臨床現場のリアルな意見交換が聞けるのはここだけ!! /
