AIが読影する時代に、技師の“責任”ってどうなるの?画像診断AIの現状と課題
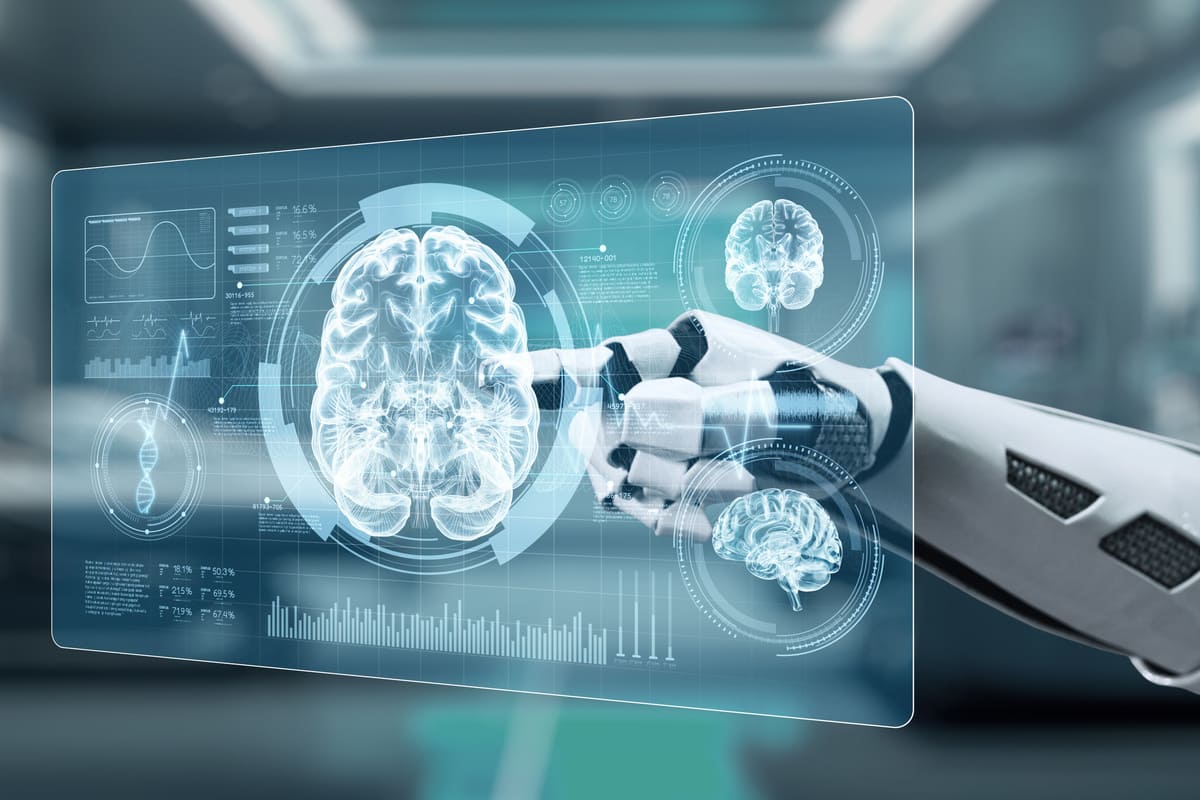
近年、医療現場においてもAIの導入が進んでおり、CTやMRIなどの医用画像を読影する「画像診断AI」も登場しています。
画像診断AIは、2018年ごろより一部で導入が進められており、読影医不足の現代において、医師の負担を軽減するソリューションとして注目されています。
今はまだ補助的な活用にとどまっていますが、今後さらに画像診断の中でAIが担う範囲が広がっていくうえでは、さまざまな課題が指摘されているのも事実です。
この記事では、画像診断AIの現状と課題を深掘りしながら、AIが読影をおこなう時代における技師の責任について考えてみましょう。
画像診断AIとは
画像診断AIとは、人工知能技術(AI)を用いて医用画像を読影するシステムです。
CTやMRIで撮影した医用画像をAIによって読み解き、異常を検出することができるもので、病変の早期発見につながることもあります。
画像診断AIは、多くの画像データをもとにした学習を積み重ねることで、医用画像に現れる微細な変化を読み取っています。
画像診断AIは医療の現場にどれくらい浸透している?
AIによる読影の精度
画像診断AIを採用するにあたり、もっとも危惧されるのは読影の精度です。
万が一、AIが病変を見逃したことによって人命に関わるようなことがあれば、どのように責任を問えるのかと考える方も多いのではないでしょうか。
2025年1月、近畿大学ではChatGPT-4o・Claude 3.5 Sonnet・Gemini 1.5 Proなどの最新モデルのAIを利用し、皮膚科専門医と診断精度を比較する研究をおこないました。
結果として、両者にほとんど精度の差はなく、AIであっても高い精度で診断を下すことができると証明されました。
画像診断AIの課題
たとえ画像診断AIに高精度の診断ができたとしても、クリアすべき課題は残されています。
徐々に画像診断AIの導入が進みつつある現代において、医療現場の方々はそれらの課題とどう向き合っていくかが問われているとも言えるでしょう。
以下では、画像診断AIが抱える課題について紹介します。
感度・特異度の限界と臨床文脈の読み取り不足
前述の研究結果からもわかるとおり、画像診断AIは、特定の疾患やパターンに対して高い感度を示します。
一方で、非典型例や、複数疾患の鑑別が必要なケースには弱い傾向があるのも事実です。
AIの場合、過去の学習データをもとに病変や異常を発見する仕組みであるため、非典型例への対応はどうしても難しくなってしまいます。
そのほかに、肺結節検出の精度は高くても、石灰化瘢痕との区別がついていないというようなこともあります。
いわば「見つける力」に長けていても、「分類する力」に乏しい状態です。
また、全体像や病歴などの臨床文脈の読み取りにも課題があり、それらを踏まえた判断は医師に委ねるべきとの意見もあります。
説明責任と判断の最終責任の所在
現在の医療制度においては、画像診断AIの読影結果が誤っていた場合、医師が責任を負う構造となっています。
そのため、AIの導入に対して慎重になることはもちろん、最終的に自身の責任である以上、AIには頼らずに自ら読影をした方が良いと考える医師も少なくありません。
また、AIが提示する結果の根拠や思考プロセスなどがブラックボックスであるために、その診断を鵜呑みにすることに不安を感じるという声も聞かれます。
疾患ごとの適応範囲が限定的
現在のAIは一疾患ごとに学習・開発されているものが多く、総合的な診断には向いていません。
実際の医療現場では、複合的な観点から医用画像を読み解く必要がありますが、特定の疾患や領域に特化したAIの場合、どうしても適応範囲が限定的になってしまいます。
たとえば、肺癌や肺結節の診断精度が高くても、肺炎や間質性肺疾患には対応していなかったりと、一つのAIでは実臨床のニーズを満たせないこともあります。
上記のような理由から、画像診断AIの導入は進んでいるものの、いまだ医師による診断がメインとなっているのが現状です。
AIが読影をする時代に技師の“責任”はどうなる?
画像診断AIの進化により、放射線技師の役割も変化しつつありますが、その中で”責任”をどのように捉えるべきかという問いは、非常に重要です。
AIが誤認した場合、「誰が責任を負うのか」が明確でない場面があります。特に、画像を提供するまたは作成する技師がAI結果を鵜呑みにして対応した場合、「専門職としての責任」が問われる可能性も考えられます。
AIの所見提示や予測に頼りすぎることなく、自らの知識・経験に基づいた確認が求められます。「AIが言っているから正しい」ではなく、「自分が確認して納得できるか」を常に問う姿勢が重要です。
実務における対応例として、胸部レントゲンにてAIが肺結節を指摘際、 技師が衣類などについてている体外物ではないかなどの確認し再撮の必要性を検討します。また、AIが異常なしと判断した場合でも、技師が経験的に「緊急性が高い」「怪しい」と感じた場合は、医師に報告するなどの必要性もあると考えます。このような医療行為が技師の業務として必要な場合は定期的なAIトレーニングやアップデート情報を共有し、技師として画像を診て判断する能力や知識を学んで訓練していく必要があります。
AI時代において、放射線技師の責任はむしろ“重く、広く”なっています。
放射線技師は、単なる撮影員ではなく、医療の質と安全を担保する「判断者」であり、責任あるプロフェッショナルであることを強く意識していく必要があると考えます。 AIとの共存の中で、必ずしも責任を回避するのではなく、「AIを使いこなす責任を引き受ける姿勢」が求められます。
遠隔画像診断サービスならY’s REPORT CLOUD
Y’s REPORT CLOUDは、日本でもっとも品質を追求する遠隔読影会社Y’s READINGが提供する遠隔画像診断サービスです。
140名以上の放射線診断専門医のうち、臨床情報や画像の内容をもとに、最適な専門医が読影をおこない、最大4重チェックを経て高品質なレポートが返送されます。
レポート返送後も、チャットによるご質問や再読影依頼などが可能で、主治医の負担を軽減しつつ、画像診断の品質を高められます。
2週間の無料トライアルも実施しているため、遠隔読影サービスの導入・乗換を検討中の方はぜひ一度お試しください。
\ 医療機関への導入実績は360施設以上!! /
