健診施設こそ遠隔画像診断を活用すべき理由とは?メリットや導入時の注意点
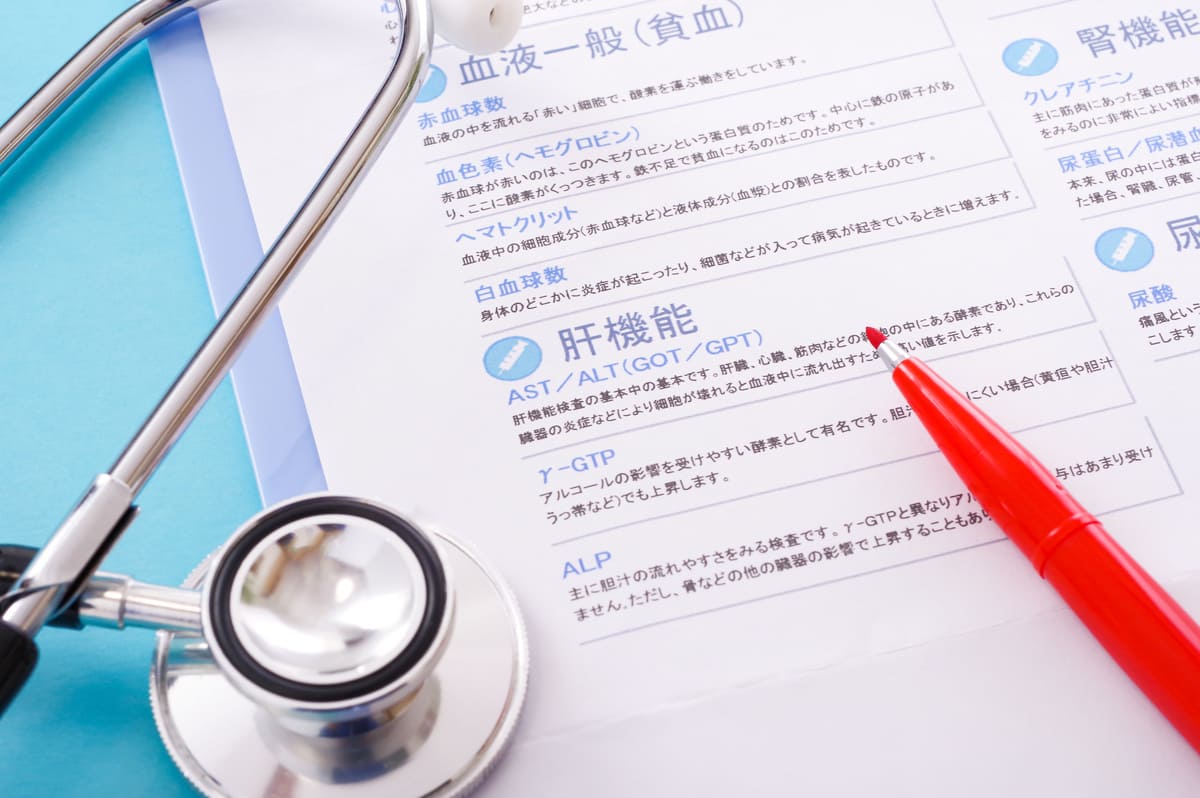
健診施設では、放射線科医の不足や繁忙期の読影件数の偏り、診断報告書作成の負担など、画像診断にまつわる課題があります。
これらの課題を解決するために、遠隔画像診断の活用が注目されています。
本記事では、健診施設における現状の課題と遠隔画像診断導入によるメリット、サービス選定時のポイントや注意点を詳しく解説します。
健診施設における画像診断の課題
健診施設では、画像診断を安定的に提供するうえで、以下のように多くの課題を抱えています。
- 読影を担当する医師の不足
- 時期によって読影件数の差が激しい
- 診断報告書の作成に時間がかかる
とくに放射線科医の不足や、繁忙期の読影件数の偏りは深刻な問題であり、診断の遅延や品質のばらつきにもつながりかねません。
以下では、健診施設における画像診断の課題を詳しく解説します。
読影を担当する医師の不足
健診施設では常勤の放射線科医を確保するのが難しく、非常勤や外部委託に頼らざるを得ないケースが多いです。
その結果、画像診断を安定的に提供できず、繁忙期には返却遅延や精度低下のリスクも高まります。
とくに地方の健診施設では、専門医が近隣にいないために依頼先が限定され、さらに課題が顕在化しやすいのも実情です。
時期によって読影件数の差が激しい
健診業務は年間を通じて均一ではなく、春から初夏、および秋の繁忙期には受診者数が増えることが一般的です。
施設によっては、通常の倍近い読影依頼が発生し、業務負担が非常に大きくなることもあります。
一方、閑散期には読影件数が減少し、検査機器の稼働率が落ちるという課題が生じます。
繁忙期・閑散期にそれぞれ異なる課題が存在し、健診施設にとっては解決が難しい問題となっています。
診断報告書の作成に時間がかかる
読影医は、読影業務だけでなく、その後の画像診断報告書の作成にも時間がかかります。
診断内容を正確かつ分かりやすくまとめる必要があり、書式や表現にも注意が求められることから、一件ごとに相応の時間が必要で、受診者に診断結果が返却されるまでのスピードにも影響します。
また、このような負担が積み重なることで、医師の労働環境の悪化にもつながりかねません。
健診で遠隔画像診断を導入するメリット
前述のとおり、多くの健診施設は画像診断においてさまざまな課題を抱えていますが、これらの課題は遠隔画像診断の導入によって解消することが可能です。
遠隔画像診断の導入は、読影体制の安定化や診断精度の向上だけでなく、院内医師の負担軽減や収益性の改善にもつながる点が大きな魅力です。
さらに、外部の専門医と連携することで診断の質が担保され、受診者の安心感や施設の信頼性向上にも寄与します。
次に、導入によって得られる具体的なメリットを解説します。
画像診断の体制の安定化
遠隔画像診断を導入することで、常勤医師が不足している施設でも安定した読影体制を確保できます。
外部のネットワークを利用して繁忙期における読影件数の急増にも対応できるほか、従量課金型の遠隔画像診断サービスを選べば、閑散期の無駄なコスト発生も避けられます。
診断結果の返却が遅延するリスクを低減しつつ、年間を通じて安定した画像診断の診断提供が可能です。
専門医の画像診断による診断精度の向上
多くの遠隔画像診断サービスでは、放射線診断専門医や経験豊富な医師が読影を担当します。
また、報告書の内容に関するチェック体制も整っており、診断制度の向上が見込めるでしょう。
とくに微細な病変や、見落としやすい異常の発見においては、専門医による診断が効果的です。
読影業務による医師の負担軽減
医用画像の読影から診断報告書の作成までを含めると、読影業務による医師への負担は少なくありません。
とくに健診施設の場合、読影業務の負担が繁忙期に集中しやすく、医師の業務過多や時間外労働などの原因となっていることも多くあります。
遠隔画像診断を導入し、業務を部分的にアウトソーシングできる環境をつくることで、医師の働き方改革のきっかけにもなるでしょう。
医療機器の稼働率改善による収益性向上
遠隔画像診断サービスは、CTやMRIなどの機器共同利用と組み合わせて利用することも可能です。
たとえばY’s READINGが提供するY’s REPORT CLOUDでは、クリニックなどの施設より依頼を受けて検索を実施する場合に、検査機関は撮影した画像をクラウド上にアップロードするだけで、依頼元施設はクラウド経由で専門医によるレポート・画像の閲覧やダウンロードが可能です。
遠隔画像診断サービスを通じて、従来の機器共同利用をより効率的に運用する取り組みが広がっています。
⚫︎関連記事:画診共同の仕組みと診療報酬の算定方法|導入手順と注意点も紹介
\ 最大4重チェックで見落としを防ぐ遠隔画像診断サービス /
遠隔画像診断サービスを選ぶ際のポイント
遠隔画像診断を導入する際には、サービス選びを慎重に行うことがポイントです。
診断体制の規模や専門性、報告書の品質、返却スピード、そして料金体系までを総合的に比較する必要があります。
以下では、健診施設が特に確認すべき選定ポイントを詳しく解説します。
健診依頼に対応できる読影体制があるか
健診施設では、春から初夏、秋の繁忙期に読影依頼が急増するため、十分な読影体制があるかどうかは重要なポイントです。
専門医の在籍人数やモダリティ別の対応可能範囲、さらに夜間や休日対応の有無など、具体的に確認しておきましょう。
柔軟に対応できる仕組みを持つサービスを選ぶことで、繁忙期でもスムーズに業務を進められます。
画像診断報告書の品質は十分か
品質の面では、画像診断の精度や、報告書のわかりやすさなどをチェックすべきです。
また、誤診や記載ミスを防ぐうえで、ダブルチェックや二次読影など、品質管理の仕組みがあるかも聞いておくと安心です。
サービスの選定時には、報告書のサンプルを見たり、トライアルを利用したりして、実際にどのような形で報告書が提供されるのかを確認しておきましょう。
レポート返却までにかかる時間はどれくらいか
読影の依頼からレポートが返ってくるまでに時間がかかると、受診者への健診結果の返却もそれだけ遅くなってしまいます。
また、急を要する読影依頼に対して、即日対応や夜間対応などのオプションが用意されているかどうかもポイントです。
最短返却と標準返却の場合の所要日数を確認し、スムーズな健診フローを組めるサービスを選ぶのがおすすめです。
料金体系はわかりやすいか
遠隔画像診断サービスには、下記のようにさまざまな料金体系があります。
- 月額料金制
- 月額料金+従量課金制
- 完全従量課金制
なお、基本料金のほかに、部位加算やスライス枚数加算などが生じることもあるため、オプションも含めてシミュレーションをしておく必要があります。
健診施設の場合、毎月の依頼件数には変動があるため、無駄なコストが発生しないよう、柔軟な料金体系のサービスを選ぶことがポイントです。
\ 初期費用・月額費用無料の遠隔画像診断サービス /
どのようなオプションが用意されているか
遠隔画像診断サービスには、標準的な読影に加え、緊急読影や再読影などのオプションが用意されている場合があります。
これらは健診施設の規模やニーズに応じて柔軟に活用できるため、サービス選定時の重要な比較ポイントになります。
また、毎月の費用にも大きく関わる部分であることから、どこまでが標準のサービスとして費用内に含まれているかもチェックしておきましょう。
⚫︎関連記事:遠隔画像診断システムは導入すべき?ベンダー選びから運用までの流れや費用は?
健診に遠隔画像診断を導入する際の注意点
遠隔画像診断には多くのメリットがありますが、導入や運用には注意すべき点も存在します。
コストやセキュリティ環境、院内の業務フロー調整といった現実的な課題を見落とすと、期待した効果を得られない可能性があります。
導入前にはリスクとデメリットを理解し、それに対する対策を講じることが重要です。
以下では、健診施設が遠隔画像診断を導入する際に特に注意すべきポイントを解説します。
導入・運用にかかるコスト
遠隔画像診断サービスを導入するうえでは、初期費用や月額利用料、通信費をはじめ、さまざまなコストが発生します。
また、スライス加算やオプションなどの追加料金が生じることもあり、場合によっては想定以上の費用となる可能性もあります。
そのため、導入前には料金シミュレーションを行い、コストと効果を比較検討しておくことで、無理のない運用を実現できます。
⚫︎関連記事:遠隔読影の費用相場は?導入・運用にかかる料金の内訳と安く抑えるポイント
インフラ・ネットワークのセキュリティ環境
遠隔画像診断においては、ネットワークを通じた臨床情報のやりとりが欠かせないため、セキュリティ環境の整備が必須です。
具体的には、暗号化通信やアクセス制限、ログ管理など、インフラやネットワークのセキュリティ環境が求められます。
導入を検討する際には、遠隔読影サービスのベンダーがどのようなセキュリティ対策を行っているかを事前に確認しておくと安心です。
⚫︎関連記事:遠隔画像診断のセキュリティ上のリスクとは?安全性や対策のチェックは必須
院内における画像診断の業務フロー
遠隔画像診断を導入すると、施設内の業務フローも大きく変わります。
画像データの送信手順やスタッフの役割分担、結果報告の確認プロセスなど、従来とは異なる動きが必要となるため、「誰が送信を担当するか」「返却後に誰が確認するか」といったフローを確認しておきましょう。
導入前に業務フローを整理し、院内全体で共通認識を持って運用できるようにしておくことがスムーズな導入のポイントです。
健診における遠隔画像診断の活用事例
次に、実際に健診施設において、どのようなシーンで遠隔画像診断を活用しているのかについて紹介します。
① 胸部X線
職員健診シーズンには、通常の倍近い胸部X線読影が集中するケースがあります。
遠隔読影を導入することで分担して対応でき、医師の業務負担軽減にもつながりました。
その結果、健診結果の説明が滞らず、報告遅延を抑えることができ、受診者にもスムーズに結果を返却できる体制が整いました。
② マンモグラフィ(二重読影対応)
マンモグラフィはガイドラインで二重読影が推奨されています。
ある健診施設では、院内で1名、遠隔で1名の放射線科医が読影する体制を導入し、ダブルチェックによって見落とし防止と診断精度の向上を実現しました。
この仕組みにより、受診者の安心感が高まり、施設の信頼度向上にもつながっています。
遠隔画像診断サービスならY’s REPORT CLOUD
Y’s REPORT CLOUDは、日本でもっとも品質を追求する遠隔読影会社Y’s READINGが提供する遠隔画像診断サービスです。
140名以上の放射線診断専門医のうち、臨床情報や画像の内容をもとに、最適な専門医が読影をおこない、最大4重チェックを経て高品質なレポートが返送されます。
レポート返送後も、チャットによるご質問や再読影依頼などが可能で、主治医の負担を軽減しつつ、画像診断の品質を高められます。
2週間の無料トライアルも実施しているため、遠隔読影サービスの導入・乗換を検討中の方はぜひ一度お試しください。
\ 医療機関への導入実績は360施設以上!! /
